こんにちは。のーちです。
今回はQC検定についての記事です。
製造業で働いている方なら一度は耳にしたことがあるQC検定。
生産技術としてのスキルアップと、統計学の勉強も兼ねて、私も資格取得を目指すことにしました!
今回は、QC検定とはどのような資格なのか、合格率や受験料、難易度やメリットについてなどをまとめてみました。
受験を考えている方や、QC検定がどんな資格か知りたい方など参考にしてみてください。
QC検定とは
QC検定とは、Quality Control(品質管理)に関する知識を問う民間資格です。
一般財団法人日本規格協会(JSA)と一般財団法人日本科学技術連盟(JUSE)が主催し、一般社団法人日本品質管理学会(JSQC)が認定します。
QC検定には4級、3級、2級、準1級、1級の5つの等級があり、それぞれ下記のような方をターゲットにしています。
QC検定®1級
QC検定®の1級受検にあたっては、組織内で発生するさまざまな問題に対して、品質管理の側面からどのようにすれば解決や改善ができるかの把握や、それを自身で主導していくことが期待され、また、自身で解決できないような問題については、どのような手法を使って解決することができるのかを考えていく力が問われます。
各企業内での品質管理活動のリーダーや、今後そのような立場に立つ方に要求される知識を有し、その活用の仕方を理解している方が受検の対象となり、難易度はかなり高いといえるでしょう。QC検定®2級
QC検定®の2級受検にあたっては、品質管理にたずさわる部署のリーダーや管理職、スタッフなどが対象となり、一般的な職場で発生する品質に関連した問題をQC七つ道具・新QC七つ道具などの統計的手法を活用して、基本的な管理・改善活動を自身が中心となって実施できるレベルです。品質管理に関して、しっかりとした知識を持ち、その時々に応じて適切な活動ができることが要求されます。
QC検定®3級
QC検定®の3級受検にあたっては、業種に関わらず職場の問題解決を行う社員の方、品質管理について学んでいる学生などが対象となり、QC七つ道具に関して作り方と使い方の理解をしているとともに、熟練者による改善の進め方の指導を受ければ、職場において発生する問題をQC的問題解決法により解決していくことができるレベルです。
品質管理に関しては基本的な知識を理解して改善を進めていけることが要求されます。QC検定®4級
QC検定®の4級受検にあたっては、品質管理の初学者や新入社員、初めて品質管理を学ぶ大学生・高専生・高校生などが対象となり、品質管理の基本を含めて企業活動の基本常識を理解しており、企業等で行われている改善活動も言葉としては理解できるレベルです。仕事全般の常識的な進め方や、品質管理に関する用語の知識は有している必要があります。
https://www.jtex.ac.jp/user_data/qc_cons01
統計の知識が必要
品質管理の手法の多くは統計学を利用しており、QC検定の試験問題を解くには統計学の知識が必要になります。
統計と聞くと難しい数学のイメージがありますが、高校レベルの数学で解ける問題がほとんどです。
QC検定を取得するメリット
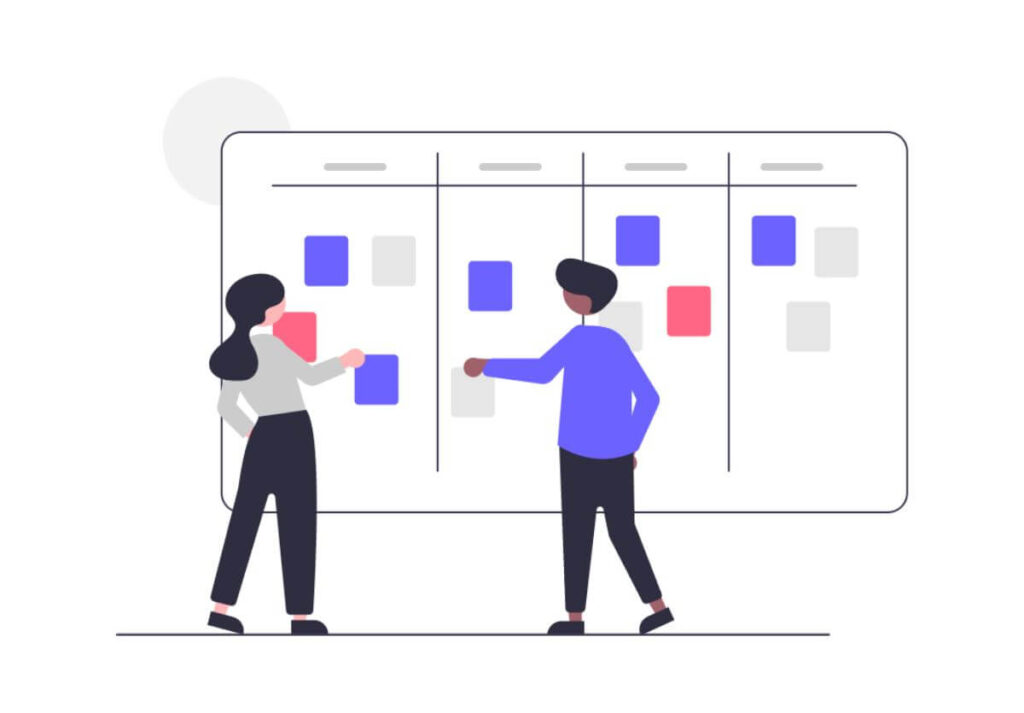
QC検定を取得していると品質管理の知識があることを証明できます。
また、QC検定に合格するには、それなりの学習とQC活動への理解が必要なので、そのことを転職活動でアピールできます。
特に2級以上は、品質管理部門のリーダーや管理職を受験対象としており、2級以上に合格していることで、品質活動において中心的や役割を担える能力があることを示すことができます。
またどの級でもQC検定合格のために学んだ品質管理の知識を、普段の品質活動に活かすことができます。
QC検定の合格率
合格率は取得する級によって異なります。
日本規格協会の発表によると、第34回(2022年)の合格率は次のようになっています。
今回の合格率は、 1級10.35%〔8.18%〕、準1級19.3%、2級25.23%〔23.77%〕、3級54.39%〔64.18%〕、4級85.89%〔85.05%〕となりました。前回と比較すると、3級で約10ポイント低下したほかはほぼ同等の結果となりました。
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0620?id=858#:~:text=%E4%BB%8A%E5%9B%9E%E3%81%AE%E5%90%88%E6%A0%BC%E7%8E%87%E3%81%AF,%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
多くの方が最初に取得を目指す3級で約50%、管理職レベルの2級で約25%ほどの合格率なので、他の民間資格と比べると取得難易度は比較的高いかもしれません。(FP2級の合格率は60%)
QC検定の受験方法
QC検定は受験資格を設けていないため、学歴や実務経験に関係なく誰でも受験することができます。
試験は年2回、3月と9月に実施されます。
申し込みは例年、受験日の3か月ほど前から開始され、1か月ほど前に締め切られるようです。
申し込みは一般財団法人日本規格協会(JSA)のホームページから行えます。
受験会場の詳細は公表されておらず、都道府県単位で会場が準備されるようですが、アクセスが良い場所とは限らないようですので、注意が必要です。
QC検定の受験料
受験料は級によって異なり、以下のようになっています。
| 受験級 | 金額 |
| 1級 | 1,100円 |
| 準1級 | 8,800円 |
| 2級 | 6,380円 |
| 3級 | 5,170円 |
| 4級 | 3,960円 |
TOEICの受験料が7,810円ですので、資格試験の受験料としては比較的親切な価格設定ですね。
QC検定ではどんな問題がでるのか
QC検定の出題サンプルは日本規格協会のサイトから確認できます。
文章の正誤を問う設問や、語群の中から選択する問題、文章や図をみて設問に答える問題などがあります。
計算問題もいくつか出題されますが、標準偏差や工程能力といった、QCに関連する統計問題がメインですので、覚えるのは難しくないと思います。
QC検定合格するためにおすすめの勉強法
過去問
まずは過去問を解いてみるのがいいでしょう。
資格試験なので、QC手法全てを覚えるよりも、問題の傾向を把握して、ピンポイントで学習するのが合格への近道だと思います。
私が購入した過去問集はこちら。
事前に勉強をしていなくても回答できる問題もありますので、自分の実力を把握するためにもまずは1回分の過去問を解くことをおすすめします。
過去問は日本規格協会から発売されていますが、毎年新版が出ますので最新版の購入をおすすめします。
参考書
QCについて体系的に学びたい場合や、過去問で分からなかった部分を学習したい場合に参考書があるといいです。
私が購入した参考書はこちら。
図も多く、解説をも丁寧なので分かりやすいです。
まとめ
QC検定は、製造業で働く方におすすめの資格です。
品質管理の手法を学ぶことができ、日々の業務や転職活動に役立てることができます。
問題を解くには統計の知識が必要ですが、学習した知識は改善活動や品質活動にも必要な知識ですので、理解を深めておいて損はありません。
私も今年中の資格取得に向けて勉強を始めました!
学習した内容や、つまずいたポイントなどを配信する予定ですので、受験を考えている方は一緒にがんばりましょう!




